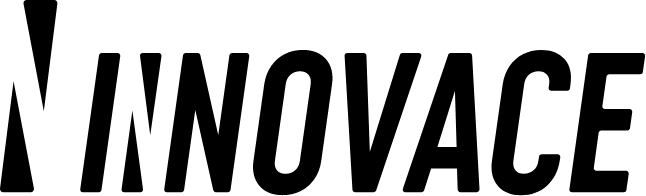For Restaurants|2024/10/18
飲食店の原価率の計算方法! コストを削減する方法も知ろう
飲食店の経営において、原価率は重要な指標のひとつです。
一般的に飲食店の原価率は何%程度が目安かご存じでしょうか。
今回は、飲食店の原価率について、計算方法やコストを削減する方法についてご紹介します。

Index
飲食店における原価率の目安は30%

業態によっても異なりますが、目安としては20〜35%を目指しましょう。
40%を超えてしまうと、その分魅力のある商品にはなるものの、利益を出せない可能性があります。
例外として集客目的で、原価1杯200円程度のビールを原価のまま売る飲食店もありますが、商品ごとの原価を計算したうえで、基本は月次週次日次とトータルで原価率を考えるのが必要です。
飲食店の原価率の計算方法
調理する上で使用する食材費や、提供するドリンクの材料費が原価です。
飲食店の原価率は以下の計算式で算出します。
原価率=売上原価÷売上高×100
飲食店の原価率は、一般的に30%以下がよいとされています。
原価率30%以下の考えは、他の経費や利益の割合を以下のように考えるためです。
・原価:30%
・人件費:30%
・家賃:10%
・水道光熱費:8%
・通信費や広告宣伝費などその他経費:12%
・利益:10%

原価率を抑える方法
利益を増やすためには、原価率を抑えることが有効です。
現状の運用を見直し、可能な方法を実践しましょう。
食材の廃棄を減らす
食材の使用量を予測して、食材の廃棄を減らします。
食材には使用できる期限があるため、廃棄を多く出すと、その分だけ原価率が上がります。
「週末は来店が多い」「時期的にこのメニューは提供数が少ない」など、過去のデータを用いて食材の使用量を予測し、適切な量の仕入れを目指しましょう。
在庫管理を徹底する
飲食店における在庫は、期限のある食材が主です。
在庫が多過ぎると、賞味期限切れや腐って廃棄することにつながります。
定期的に棚卸しを行い、どの食材がどれだけあるのかの把握が重要です。
在庫量と今後の売上予測を踏まえて仕入れる量を調整することで、廃棄を減らせます。
在庫は多過ぎず少な過ぎず、使用量の動向を見ながら管理を徹底しましょう。
料理に使用する食材の量を決める
料理に使用する食材の量を決めて守ることも、原価率を下げることにつながります。
決められた分量よりも多く盛り付けて提供するオーバーポーションは、原価率の上昇につながります。
調理をするスタッフ一人ひとりが決められた量を守ることが重要です。
料理の価格を見直す
原価を抑えることが難しい場合は、料理の価格を見直すことでも、原価率を抑えられます。
「なるべく安く提供したい」「高くすると顧客が離れるのでは」などの理由から、価格を上げることに抵抗を感じる場合もあるでしょう。
しかし、食材が値上がりしたにも関わらず売価を維持すると、原価率は上がります。
食材の値上がりが一過性のものであれば、一時的に耐えることも選択のひとつです。
恒常的に上昇する場合は、適切な原価率をもとに料理の価格を見直しましょう。
原価率の低いメニューを増やす
原価率を下げるために、原価率の低いメニューを増やす方法もあります。
例えば、居酒屋の冷奴やハンバーガー店のフライドポテト、ケーキ屋のショートケーキなどは、原価率の低いメニューです。
サイドメニューは比較的減価率の低いメニューが多くあります。
他にも、原価率の低いドリンクとセットにしたメニューを作ることは手軽にはじめられる方法です。
今あるメニューを工夫することでも原価率を抑えたメニューを増やすことができます。
客単価を上げる工夫をする
客単価とは、顧客1人当たりの売上の平均です。
原価率が低くても、客単価を上げて売上が上がれば、利益は増えます。
客単価を上げる方法としては、セット販売が有効です。
ドリンクセットや、追加料金で選べるオプションやトッピングなど、追加注文しやすい工夫をしましょう。

原価率だけでなくFLコストも重要
FLコストとは、「FOOD(材料費)」と「LABOR(人件費)」をあわせた費用です。
飲食店の売上のうち、FLコストが占める割合は重要な指標です。
つまり、原価率とともに人件費も適切にコントロールする必要があります。
FLコストの目安は50%~60%です。
もし60%を超えている場合は、原価率だけでなく人件費の見直しも検討しましょう。
飲食店にかかるコストを削減するコツ
利益を増やすためには、原価率だけでなく、不要なコストを削減する必要があります。
そこでここからは、そのためのコツをご紹介します。
業務を見直す
現在の業務を見直し、システムの導入など効率化できることを検討しましょう。
例えば、注文や会計にかかる時間を減らせれば、スタッフの作業時間を短縮可能です。
モバイルオーダーやセルフレジの導入など、DX化を進めることでこれらの業務はなくせます。
飲料水は顧客が給水機へ取りに行く、配膳を顧客自身に行ってもらうなど、セルフサービスを取り入れる方法も業務効率化の一環です。
柔軟にシフトを組む
飲食店は、忙しい時間帯と暇な時間帯に差があります。
昼食や夕食のピーク時と、それ以外の時間帯では人数にメリハリをつけ、それぞれに必要な人数のスタッフを配置しましょう。
他にも、急な大雨や大人数の予約キャンセルなど、想定外の状況が起きた場合は、早上がりなどシフトを変更して対処しましょう。
シフトを臨機応変に変更できると人件費の効率化につながります。
システムを導入する
システムの導入で業務を効率化できると、スタッフの業務負担が軽減され、人数を減らすことができるので人件費も抑えられるようになります。
例えば、モバイルオーダーを導入すればスタッフが注文を受けに行く作業は不要です。
セルフレジやキャッシュレス決済を導入することで、レジ業務が不要になったり会計時間を短縮できたりします。
POSレジを導入すれば、販売データや売上データの集計や分析にかかる時間を短縮できます。
業務をシステム化することで、スタッフの負担が軽減されるだけではなく、人件費の削減が可能です。

まとめ
飲食店向けの決済アプリ「L.B.B Register」は、これひとつでモバイルオーダーの注文管理やPOSレジ、分析機能などさまざまな機能が使えます。
これらはすべて月額料金で利用できるため、各システムを導入するための費用を大きく削減できます。
また、モバイルオーダーやPOSレジを活用することで、業務の効率化や人件費の削減が可能です。
飲食店のDX化やコスト削減は、LBBにご相談ください。
Most Popular Posts
RECOMMEND
For Restaurants|2025/11/28
飲食業界におけるAIエージェントの役割──人手不足の時代を支える“デジタルスタッフ”とは?
2025年、飲食業界は転換点を迎えています。慢性的な人手不足、採用難、定着率の低下──。
現場が抱える構造的な課題に対し、今注目されているのが“AIエージェント”という新しい解決手段です。
この記事では、AIエージェントが飲食現場で果たす具体的な役割と、なぜ今それが必要とされているのかを解説します。
For Restaurants|2025/11/27
2025年は「AIエージェント元年」──いま浸透が進んでいる業界と、その理由
2025年は“AIエージェント元年”と呼ばれています。
ChatGPTやClaude、GeminiなどのLLM(大規模言語モデル)が業務に組み込まれはじめ、さまざまな業界で「AIに業務の一部を任せる」動きが本格化。
単なる“チャットボット”とは異なり、ユーザーの文脈や履歴、データベースと連携し、実際に“行動”するAIが、いま広がりを見せています。
では、どの業界で先行して導入が進んでいるのでしょうか?
For Restaurants|2025/11/26
AI日報を“使える武器”にするには?──飲食店のための準備と活用ステップ
「AIが自動で日報を作ってくれるらしい」──そう聞いて興味を持ったものの、実際に導入しても「思ったほど活用できなかった」という声が少なくありません。
では、何が足りなかったのでしょうか?
それは、「データを活かすための準備」と「使い方の設計」です。
この記事では、L.B.B.CloudのAIエージェントを使って、飲食店の日報業務を本当に楽にし、売上改善にもつなげるための現実的なステップを紹介します。